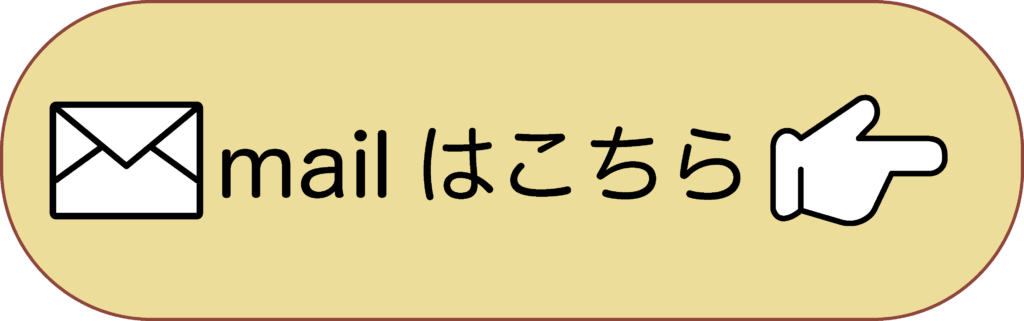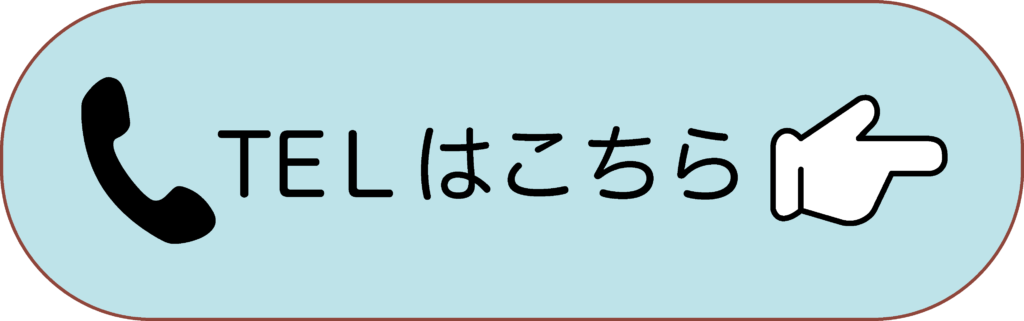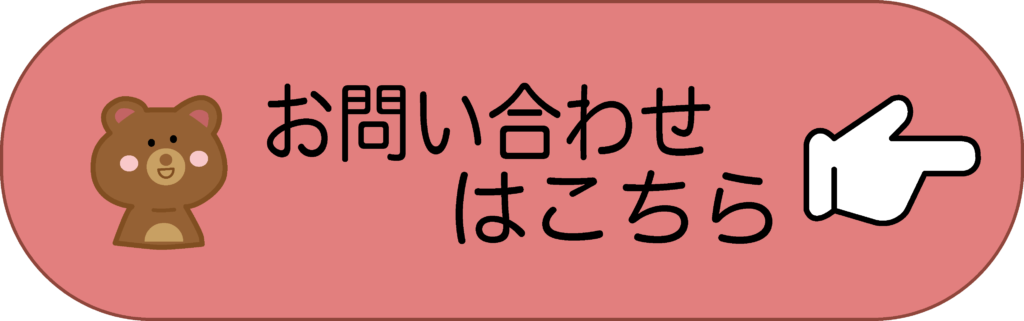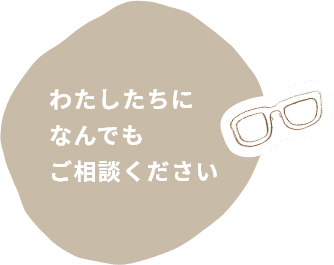こちらのページでは、オンラインショップにてご注文のお客様より
お問い合わせの多いご質問について紹介いたします。

ご注文について
Q .
注文したのですが確認のメールや電話連絡がきていません。
A .
ご注文を頂いてから、1営業日以内にお客様のメールに確認メッセージを送っております。
1営業日以内にメールが届いていない場合は、お早めに当ショップまでご連絡ください。

Q .
携帯のキャリアメールを利用して注文できますか?
A .
可能ですが、弊社PCからのメールが届かない場合があります。
LINEをお使いの方は、LINEの登録をお願いしています。
データ送信(データ入稿)もLINEからできて大変便利です。

Q .
「価格表にサイズがないのですが...」
「数量がかなり多いのですが...」
こんな追加オプションには対応できますか?
A .
価格表にないサイズや数量が多い場合、追加オプションにつきましては、
別途お見積をさせていただきます。下記お問い合わせフォームよりお見積依頼してください。
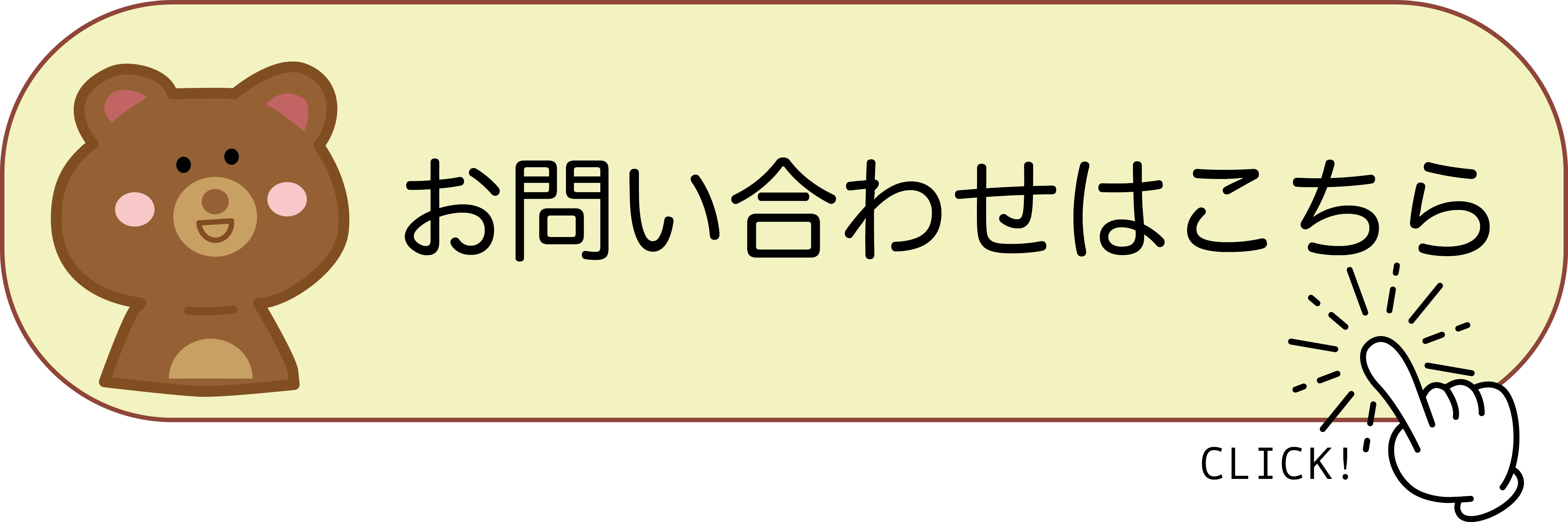

データ入稿について
Q .
スマホしか無いのですが、入稿(データ送信)はできますか?
A .
スマホからのデータ送信も対応しております。おすすめは便利なLINEの友だち登録です。印刷前確認のやりとりなどもLINEで完結できます。

Q .
LINE登録すれば入稿しやすいですか?
A .
LINE・メール・お問い合わせフォームにてデータの受付や、お問い合わせの対応をさせていただいております。
お客様が慣れている方法をお選びください。
もちろん電話対応も大丈夫です。

Q .
過去に依頼した際のデータと同じものを作って欲しいのですが大丈夫ですか?
A .
ストアスタッフがレイアウトデザインを行なったデータは6か月間保管してあります。お客様からのご入稿データは1ヶ月間保管しております。
また、データの編集等は有料で行っております。

Q .
データを扱うソフトの種類を教えてくれませんか?
A .
画像JPEG、Office(オフィス)ソフト、Adobe Illustrator・Adobe Photoshopなど、他もPDFにできるソフトであれば対応できる場合があります。 一度ご連絡ください。

Q .
出力はWordやExcelなど、Office系データに対応していますか?
A .
はい、対応しております。ただし、書体がない場合はご連絡いたします。
アウトラインの方法やPDFに書き出して保存する方法をお伝えします。

Q .
画像の解像度はどれくらいで送れば良いですか?
A .
原寸サイズで72dpi以上が目安になります。

Q .
デジカメのデータは大判出力に対応していますか?
A .
対応しております。JPEGデータにて入稿してください。サイズについては一度ご連絡ください。

Q .
RGBに対応していますか?
A .
弊社のインクジェット出力はCMYKもRGBも印刷可能です。
ご指定がある場合は、RGBかCMYKを明記してください。
※印刷時にモニターで見ている色と多少の色の違いがでる場合もございます。
100%の色の再現はできかねますのでご了承ください。

Q .
原稿の拡大縮小をしてくれますか?
A .
基本的には原寸大でのデータでお願いいたします。
サイズをご指定頂ければ原寸サイズにしてデータが適切であるかご連絡いたします。
レイアウトの限界などで原寸大での入稿が出来ない場合は、メール、電話でご連絡ください。
(追加料金は内容によって発生する場合があります)

Q .
データが重くて送れないのですが…
A .
1回の入稿データが10MB以下の場合は、入稿フォームからの入稿か、メールにてお願いいたします。
⚫️入稿フォームURL https://ca-d.net/contact-yahoo
⚫️メールアドレス info@ca-d.net
10MBを超える場合は、外部ストレージサービスをご利用ください。
弊社で通常お願いしているサービスですが、送信方法は異なりますので、
それぞれのサイトにてご確認ください。
Giga File便 https://gigafile.nu/
firestorege https://firestorage.jp/
上記サイトは弊社が管理しているサイトではございません。
アップロードをした後、アップロードデータを共有する為のURLを弊社までお知らせください。

Q .
CDやDVDでの入稿もできますか?
A .
メモリスティック(USBなど)はお断りしています。
CD・DVDの返却は基本行いませんのでご了承ください。
確認用見本データの添付もお願いします。(PDFや画像データなど)

一度入稿したデータに修正がある場合
Q .
データに誤りがありました。修正できますか?
A .
印刷確認へのご返答前なら変更可能です。印刷前確認への「確認OK」のご返答後はデータの再入稿とキャンセルは不可となります。
一度印刷してしまいますとデータの修正はできません。再入稿をよろしくお願いいたします。
(追加料金は別途見積いたします)

看板の仕様について
Q .
看板に巻き込み貼りとあったのですが、耐久性が違うのですか?
A .
耐久性は50%ほど上がります。板からの剥がれがかなり抑えられます。
表面の耐久性は同じです。

配送について
Q .
時間指定はできますか?
A .
西濃運輸で発送いたします。時間希望はできますが指定はできません。

Q .
北海道、沖縄、離島は別途追加料金必要とありましたがどのくらいかかりますか?
A .
配送先の住所を確認して、料金をお知らせいたします。
弊社で決済前に料金を修正させて頂き、ご了承を経てから製作いたします。

キャンセルについて
Q .
注文の時点で決済されるのですか?
A .
校了前までは決済されません。(支払方法によっては、注文時に決済となります。)
決済後は制作段階に入っていますとキャンセルできない可能性があります。

Q .
注文したのですが、データができていません。
いつまで待ってもらえますか?
A .
ご注文後1週間以内に入稿(データ送信)をお願いします。
それ以降はお客さま都合のキャンセルとさせていただきます。
その場合は使われたポイントは返却できません。ご了承願います。

Q .
注文後、オプションの追加等で金額が増額した場合はどうすればいいですか?
A .
弊社で追加金額の修正をさせていただきます。クレジットの場合は自動で決済されます。
PayPayで購入されたお客様へは別途案内させていただきます。
ゆっくり払いを選択された場合は、金額変更ができません。
一度キャンセル処理を行いますので、再度ご注文お願いします。

Q .
PayPayで注文したのですが追加料金はどのように支払えばよろしいですか?
A .
オプションの追加料金を連絡させていただきます。
一旦、購入金額+オプション金額をプラスした金額をチャージしてください。
決済後、オプション代金を引落とし、購入代金は返却されます。
*最初の購入代金の2重引き落としにはなりません。
その他、ご質問がございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。